法的な効力を持つ書面の作成が必要
空き家になりそうな家屋を相続することになりそうな場合、所有者が遺言書を作成しておいてくれると、方針は明確になります。ただし、遺言書は作成方法など厳格な決まりがあります。近年、「エンディングノート」は終活の一環として広く利用されていますが、法的効力は基本的にありません。
エンディングノートは、自分の希望や思いを家族や関係者に伝えるためのものですが、遺言書のように法律で定められた効力を持つものではないという点に注意が必要です。遺言書は民法という法律に基づいて作成する書面であり、亡くなった人の最後の意思表示です。法律では、遺言によって自身について相続が開始した際の相続財産の行く末についての指定ができるほか、認知など、一定の身分上の行為を行うことが認められています。
両親の死後、遺された家族の間で揉めそうな場合、あるいは現時点で連絡がつきにくい家族がいる場合などは、エンディングノートから一歩進めて、法的な効力を生じさせる遺言書の作成が必要になります。
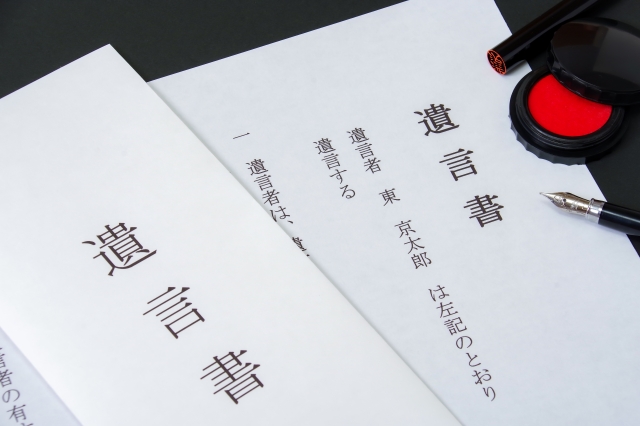
遺言書の種類
民法では、遺言に関してさまざまな規定が設けられています。中でも、基本的な方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類が定められています。注意すべき点として、たとえ故人が思いを込めて書き遺した遺言書であっても、法律で定められた方式に従っていない場合、原則としてその遺言は無効とされてしまいます。したがって、これらの遺言の方式について正しく理解し、確認しておくことが重要です。
自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、これに押印して作成する遺言書のことです。その内容はすべて遺言者自身が手書きで記載しなければなりません。ただし、相続財産の目録(一覧表)については、自筆ではなく、パソコンやワープロで作成したものや、資料のコピーを用いることも認められています。この目録には、すべてのページに遺言者の署名と押印が必要です。
一方、公正証書遺言は、公証役場において公証人の面前で遺言の内容を口頭で伝え、その内容を公証人が筆記して作成するものです。法律の専門家である公証人が関与するため、形式の不備などによって無効になるリスクが少なく、また保管も公証人が行うため、多くの人に利用されています。
自筆証書遺言保管制度とは
自筆証書遺言書は、紙とペン、印鑑があれば特別な費用もかからず1人で作成できます。しかし、せっかく遺言書を作成しても、一定の要件を満たす必要があり不備があると無効になってしまう場合があります。また、自宅で保管している間に、遺言書が改ざん・偽造されたり、紛失したりするおそれもあります。さらには、遺族が遺言書の存在に気がつかないということもあります。
そこで、自筆証書遺言の手軽さなどの利点を生かしつつ、こうした問題を解消するため、自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」が、令和2年(2020年)7月10日からスタートしています。この制度は、全国312か所の法務局で利用することができます。

自筆証書遺言書保管制度のメリット
(1)適切な保管によって紛失や盗難、偽造や改ざんを防げる
法務局で、遺言書の原本と、その画像データが保管されるため、紛失や盗難のおそれがありません。また、法務局で保管するため、偽造や改ざんのおそれもありません。それにより、遺言者の生前の意思が守られます。
(2)無効な遺言書になりにくい
民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて法務局職員が確認するため、外形的なチェックが受けられます。ただし、遺言書の有効性を保証するものではありません。
(3)相続人に発見してもらいやすくなる
遺言者が亡くなったときに、あらかじめ指定されたかたへ遺言書が法務局に保管されていることを通知してもらえます。この通知は、遺言者があらかじめ希望した場合に限り実施されるもので、遺言書保管官(遺言書保管の業務を担っている法務局職員です。)が、遺言者の死亡の事実を確認したときに実施されます。これにより、遺言書が発見されないことを防ぎ、遺言書に沿った遺産相続を行うことができます。
(4)検認手続が不要になる
遺言者が亡くなった後、遺言書(公正証書遺言書を除く。)を開封する際には、偽造や改ざんを防ぐため、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要があります。この検認を受けなければ、遺言書に基づく不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができません。しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認が不要となり、相続人等が速やかに遺言書の内容を実行できます。
遺言書作成の重要性と注意点
遺言書は、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを生前に明確に示すための重要な書類です。法律では、遺言書の形式に一定のルールが定められており、これを守らないと、せっかく作成しても効力を持たない「無効な遺言書」になってしまう可能性があります。
1. 自筆証書遺言の基本ルール
最も一般的で手軽な遺言書が「自筆証書遺言」です。しかし、この方法には以下の要件があります。
- 全文を自筆で書くこと
→ パソコンや代筆は不可。全文を本人の手で書く必要があります。 - 日付を正確に記入すること
→ 「令和○年○月○日」など、特定できる形で明記する必要があります。日付がない、または「○月吉日」など曖昧な表記は無効となる可能性があります。 - 氏名を自署すること
→ 本人が自分の名前を自筆で書くことが求められます。押印だけでは足りません。 - 押印(印鑑を押す)こと
→ 実印・認印どちらでも構いませんが、押印を忘れると遺言書として無効になります。
2. 遺言書がない場合のリスク
遺言書が存在しない場合、故人がどのように財産を分けたかったのかが不明なままとなります。その結果、残された相続人の間で意見が食い違い、深刻なトラブルや争いに発展することもあります。特に財産が多い・相続人が複数いる・再婚や特定の相手に譲りたい希望がある場合などは、遺言書の有無が大きな影響を及ぼします。
3. 公正証書遺言という選択肢
「公正証書遺言」は、公証人が本人から遺言の内容を聞き取り、法律に則って作成してくれるため、形式の不備によって無効になる心配がほとんどありません。さらに、遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんといったリスクも避けられます。
公正証書遺言は手間や費用は多少かかりますが、その分、法的な有効性や安全性が非常に高い方式です。大切な遺産を確実に希望どおりに残したいとお考えであれば、公正証書遺言の作成を検討されると良いでしょう。自筆証書遺言は手軽な反面、形式不備による無効のリスクが高いため、確実性を求めるなら「公正証書遺言」の選択肢もあります。

まとめ
このように、相続によって空き家を引き継ぐ可能性がある場合には、事前に所有者が明確な意思表示をしておくことが、残された家族にとって大きな助けとなります。エンディングノートは、自身の希望や思いを伝えるための有効なツールですが、法的効力がないため、相続や財産の分配に関しては、遺言書を正しい形式で作成しておくことが非常に重要です。
遺言書は、法律(民法)に基づいて作成する必要があり、その方式にも「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。これらの形式に従っていない遺言書は、たとえ本人の強い意思が込められていたとしても、無効とされるおそれがあります。
相続をめぐるトラブルや空き家問題を未然に防ぐためにも、遺言書の作成にあたっては、その方式や内容についてしっかりと理解し、必要に応じて専門家に相談しながら準備を進めることが大切です。円満な相続と安心できる将来のために、早めの対策を心がけましょう。


