親の認知症が原因で空き家が増加?
空き家の活用が進まないケースでよく見られるのは、所有者(親)が認知症などの病気を発症し、意思能力が制限される場合です。特に親が施設に入居したり、介護が必要になったりする状況では、子どもたちは「もう家に戻ることはないだろう」と考えることが多いでしょう。
しかし、時間が経過するにつれて、親との意思疎通が難しくなり、場合によっては完全に意思が通じなくなってしまうこともあります。このような状態では、家を売却したいのか、あるいは賃貸に出したいのか、そのまま残したいのか、判断が難しくなります。

親が重度の認知症になってしまい意思疎通が取れなくなった場合には、子供であっても勝手に親名義の空き家を賃貸に出したり、売却することはできません。また、大規模なリフォームなどもできません。親が重度の認知症となってしまった場合でも、成年後見制度の活用などで空き家を売却できる場合もありますが、売却の必要性がなければ家庭裁判所に認められない可能性もあります。
厚生労働省の推計によると、2025年には高齢者の5人に1人が認知症を患うことになるとされています。認知症の高齢者が介護施設に入居するケースが増えるため、住んでいた家が空き家となることが多くなります。その結果、空き家の管理や処分を進めようとしても、本人の意思確認ができず契約ができないという問題が生じ、空き家が増加する原因となっています。
認知症になる前の対策が必要
2020年に施行された改正民法では、「意思能力がない場合、その法律行為は無効とする」と明記されています。この意思能力を欠くとされる主な対象は、認知症の方です。この改正は、認知症の方々の財産を守るためにも重要な役割を果たします。
例えば、ある人が自宅の不動産を売却する契約を結んだ後、その人が認知症であることがわかれば、その契約は無効とされます。これは、高齢者を狙って不正に取引を持ちかける業者に対する規制の一環とも言えるでしょう。
しかし、認知症の親を持つ家族にとって、この改正は不動産取引の際にハードルとなる可能性があります。もし本人が「売却したい」と言っても、すでに認知症と診断されている場合、不動産会社や行政機関はその意向を受け入れないことになります。
そのため、実家の不動産について何らかの活用・処分を考えている場合、所有者が認知症になる前に対策を取ること、または認知症になった後に適切な手続きを考えておくことが必要になります。
認知症になる前にできる対策は「家族信託」と「任意後見制度」の2つ
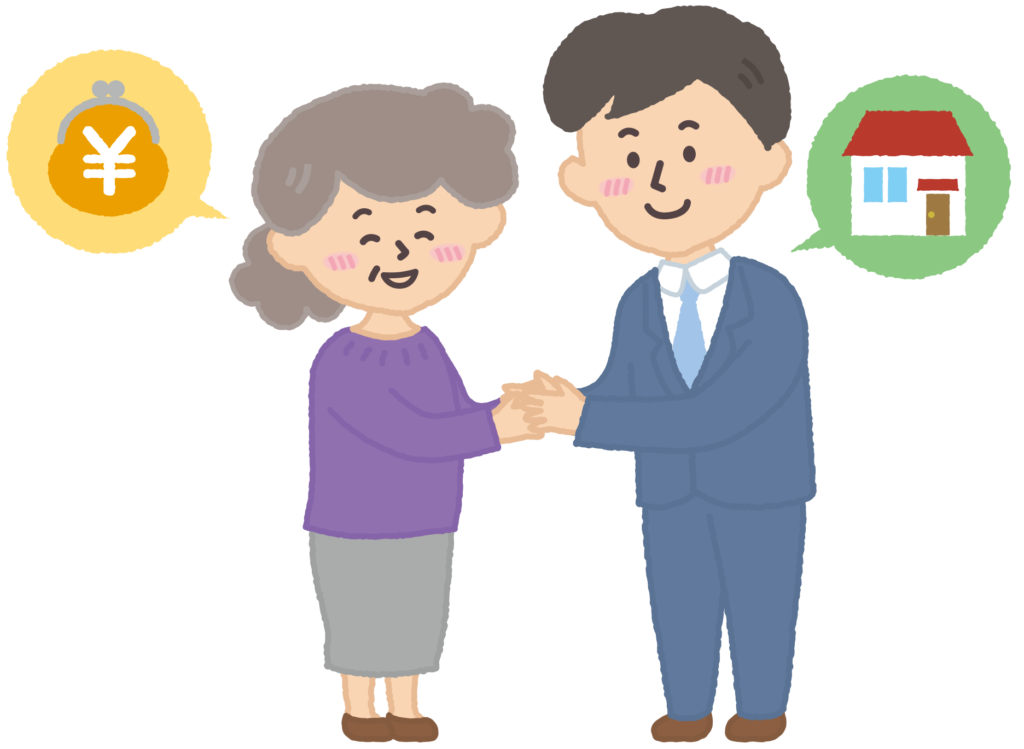
「家族信託」というのは、今財産を持っている人(委託者)が、自分の信頼できる親族(受託者)に財産の管理や処分を任せる仕組みです。
契約を結んだ後、委託者が認知症になったり、万が一亡くなった場合でも、その人の希望に合わせた財産の管理が続けられます。たとえば、不動産も信託契約に従って賃貸したり、売却したりすることができます。
家族信託は、親子だけでなく、親族間でも契約ができるため、柔軟で負担が少ない財産管理が可能です。しかし、この制度自体があまり広く知られていないのが現状です。
「任意後見制度」は、元気なうちに信頼できる人をあらかじめ後見人として選び、本人の判断能力が不十分になった後にその後見契約を結んでおく仕組みです。
例えば、将来の生活資金を確保するために自宅を売却したいと考えている場合、その売却権限を契約に含めることもできます。万が一、本人の判断能力が低下した時に備えて、信頼できる後見人がその役割を果たすことができるようになります。
判断能力が低下した後に対応する制度が「法定後見制度」
認知症になり判断能力が低下した後に対応するための制度として「法定後見制度」があります。この制度は、家庭裁判所が成年後見人を選任し、財産管理を行う仕組みです。この制度の目的は、判断能力が不十分な人が不正に財産を扱われないようにすることです。家庭裁判所への申立てには時間と費用がかかり、申立てから後見人が決まるまで、場合によっては半年ほどかかることもあります。
法定後見人を家族にしてほしいと希望しても、必ずしも認められるわけではなく、家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選ばれることもあります。また、後見人が選任された後は、後見人を変えたり解任したりするのは、後見人に不正や怠慢がない限り、簡単には認められません。基本的に、後見業務は本人が亡くなるまで続き、その間にかかる費用もあります。
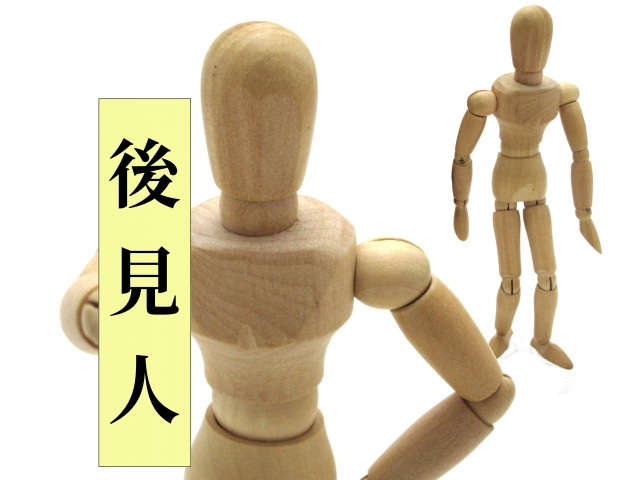
後見人には毎月の費用が発生します
成年後見制度には、費用がかかることを理解しておくことが重要です。まず、後見人を選任するためには家庭裁判所に後見開始の申立てを行う必要があり、申立てには費用がかかります。この費用は無料ではありません。
さらに、成年後見人の報酬は生涯にわたって発生します。成年後見人が家族の場合、その報酬を請求するかどうかは自由ですが、弁護士などの専門家が後見人になると、報酬が請求されます。報酬の額は自由に決まるわけではなく、家庭裁判所が金額を決定します。専門家が後見人の場合、月額2万円以上、年間で最低でも24万円程度が必要です。この報酬は、本人の財産から支払われます。
また、家族が後見人に選任されても、後見監督人が選任される場合があり、その場合も報酬が発生します。後見監督人は、成年後見人を監督する役割を担います。後見監督人の報酬額も家庭裁判所が判断します。

成年後見制度は、本人を保護するための制度であり、家族の意思で停止することはできません。基本的に、成年後見は本人が亡くなるまで続きます。例外的に、本人の判断能力が回復した場合に終了する可能性がありますが、その確率は低いです。また、目的が達成されても成年後見は終了することはありません。
このように、成年後見制度にはさまざまな費用がかかることを事前に把握しておくことが重要です。そのため、認知症が進行し判断能力が低下する前に、親の財産や不動産に関して適切な対策を講じておくことが、非常に大切だと言えます。特に実家の不動産については、親が判断能力を保っているうちに、家族間での合意を得て、空き家になるのを避ける対策を検討することが望ましいです。


